NEWS お知らせ・コラム
職人が独立しやすい仕事7選!失敗しないためのコツや準備も解説

職人の世界では、個人で働く“一人親方”として独立し、年収アップや自由な働き方を実現させる人が増えています。
しかし「どの仕事が職人として独立しやすいの?」「自分に向いてる仕事ってあるのかな……」と悩み、独立に一歩踏み出せない方も多いでしょう。
そこで今回は、職人が独立しやすい仕事を7つ厳選し、それぞれの仕事内容・年収・向いている人などをわかりやすく解説します。
独立を成功させる5つのコツも紹介するので、この記事を参考にしながら独立までの道筋を立てていきましょう。
\林業は研修・支援制度が充実◎/
\自然のなかでのびのび働こう/
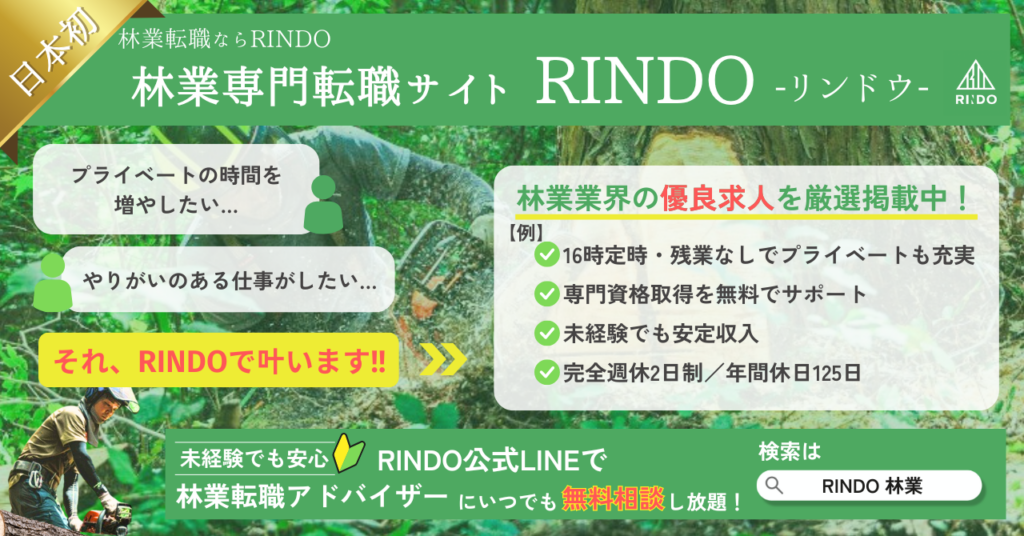
![]()
- 目次
- なぜ今、職人の「独立」が注目されているのか?
- 職人が独立しやすい仕事の3つの共通点
2-1|スキルや資格で「差別化」しやすい
2-2|一人で完結する業務が多い
2-3|初期費用が比較的少ない- 職人が独立しやすい仕事7選
3-1|大工
3-2|クロス職人
3-3|タイル職人
3-4|左官屋
3-5|塗装屋
3-6|配管工
3-7|電気工事士- 職人が独立を成功させるコツ・準備5つ
4-1|現職でスキル・人脈を深めておく
4-2|必要な資格をあらかじめ取得する
4-3|開業資金と生活費を確保しておく
4-4|副業や休日起業で試してみる
4-5|集客や営業力を磨く
- 独立経験者のリアルな声〜職人10年目の起業〜
- 職人が独立しやすい仕事でよくある質問
6-1|職人は独立したほうが儲かる?
6-2|職人が独立に失敗する原因って?
6-3|建設業で独立しやすい仕事は?- まとめ
なぜ今、職人の「独立」が注目されているのか?
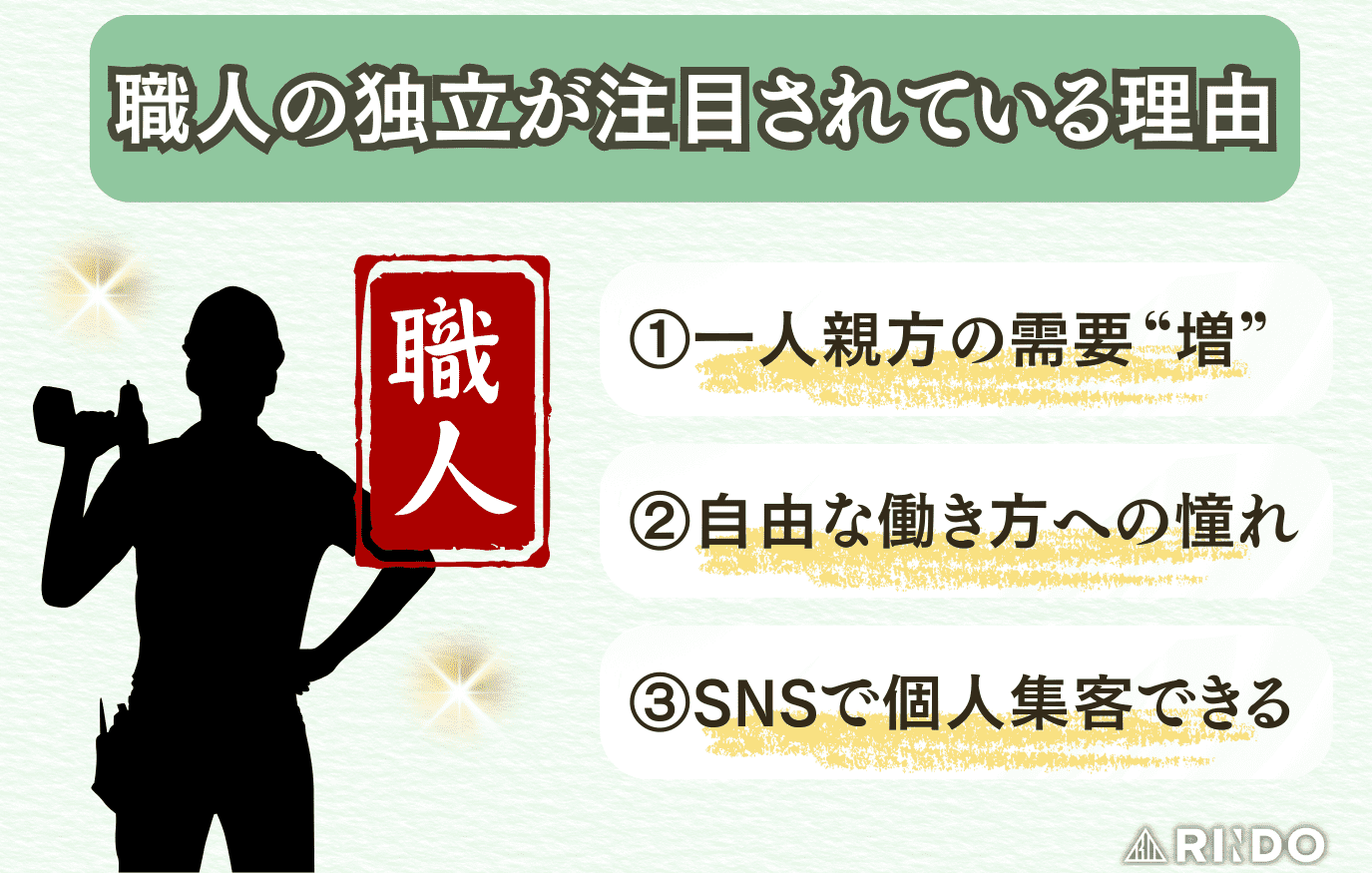
近年、職人の「独立」が注目されています。考えられる理由は次の3つです。
- 「一人親方」の需要が増えた
- 働き方の自由度を求める人が増えた
- SNSで個人でも集客できる時代になった
国土交通省によると、建設業就業者のうちの35.9%の人が、55歳以上の高齢者です。
今後10年間でベテラン人材がどっと引退する見込みで、企業は外部の一人親方(=個人職人)に仕事を依頼するケースが増えています。
また、コロナ禍をきっかけに働き方を見直す人が増えたことや、SNSの普及で個人でも仕事を取りやすくなったことも、職人の独立が注目されている理由です。
職人が独立しやすい仕事の3つの共通点

職人の仕事はたくさんありますが、独立しやすい仕事には次の3つの共通点があります。
- 専門スキルで“差別化”しやすい
- 一人で完結する業務が多い
- 初期費用が比較的少ない
自分にぴったり合う仕事を選べるよう、下記でそれぞれの特徴をみていきましょう。
①スキルや資格で「差別化」しやすい
職人が独立しやすい仕事の共通点1つ目は、専門スキルや資格で“差別化”しやすいことです。
専門スキルや資格があると、ほかの職人や業種と差別化しやすく、業界での需要が向上&安定します。
たとえば、人々の暮らしに欠かせない“電気”を家や建物に通すためには、国家資格である「電気工事士」の資格が必要です。電気工事士の資格がないと、基本的に電気工事はできません。
このように、特定の業務に関して専門的なスキルや資格をもっていると、その業界でのライバルが減り、仕事をほぼ独占状態で受注できます。
②一人で完結する業務が多い
職人が独立しやすい仕事の共通点2つ目は、一人で完結する業務が多いことです。
一人でも完結する仕事には、主に次のようなメリットがあります。
- 人件費がかからない
- 少ない開業資金で独立できる
- 人間関係のストレスが少ない
- 仕事量やスケジュールを管理しやすい など
たとえば、室内に壁紙(クロス)を貼る「クロス職人」は、基本的に一人でもできる仕事です。大がかりな現場でなければ誰かを雇う必要もなく、材料費+技術料がそのまま自分の収入になります。
一方で、チーム作業が前提となる仕事では、人件費や人材確保の負担がかかります。
チーム仕事では独立のハードルがあがってしまうため、職人として独立したい場合は一人でも完結する仕事から始めて、少しずつ事業を拡大していくとよいでしょう。
③初期費用が比較的少ない
職人が独立しやすい仕事の共通点3つ目は、初期費用が比較的少ないことです。
初期費用が少なければ、資金調達のハードルが下がります。独立しやすくなるのはもちろんのこと、万が一失敗したときのリスクを最小限に抑えられるでしょう。
たとえば、建設業と土木業の「初期費用」「独立のしやすさ」には、主に次のような違いがあります。
| 建設業 (内装、左官、電気工事など) |
初期費用がかさみにくく、職人として独立しやすい。工事の規模が小さく、コンパクトな道具や機械の用意で済むことが多いため。 |
| 土木業 (道路工事、土砂の運搬など) |
初期費用がかさむため、職人として独立しにくい。工事の規模が大きく、大がかりな重機や大型トラックなどの用意が必要になるため。 |
建設業では業種によって、工具一式と軽トラがあれば独立できるものもあります。
初期費用が少ない仕事を選ぶことで資金面での余裕が生まれ、独立への第一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
職人が独立しやすい仕事7選

ここからは、職人が独立しやすい仕事を厳選して7つご紹介します。それぞれの仕事内容・年収・向いている人の特徴まで詳しくみていきましょう。
※独立後の年収は個人のスキルや経験にもとづくため、ここでは「独立前の年収の目安」をご紹介しています。
①大工
大工は、建物を建てたり修理したりする職人です。
一人前になるには5年〜10年の修行が必要になりますが、独立すれば収入アップ&自由な働き方を実現できます。
大工の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・設計図の読み解き ・骨組みの組み立て ・木材の加工 ・建具の取り付け など |
| 必須の資格 | なし |
| あると役立つ資格 | ・建築大工技能士 ・二級建築士/木造建築士 ・木造建築物の組立て等作業主任者 など |
| 年収の目安(独立前) | 約448万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・手先が器用 ・体力に自信がある ・ものづくりへの情熱がある |
| 向いていない人の特徴 | ・細かい作業が苦手 ・肉体労働が苦手 ・コミュニケーションが苦手 |
厚生労働省によると、大工のうちの64.6%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
スキルの習得には5年〜10年と時間がかかるものの、スキルさえあれば仕事に困らないのが大工のメリットです。
ただし、大がかりな現場では複数人で作業することもあるため、コミュニケーションが苦手な人は注意しましょう。
②クロス職人
クロス職人は、室内に壁紙(クロス)を貼る仕事です。
内装現場では常に必要とされる業種のため、スキルや経験を積めば、独立後も仕事が途切れる心配は少ないでしょう。
クロス職人の主な仕事内容、年収、向いている人などは次のとおりです。
| 主な仕事内容 | ・古いクロスの撤去 ・下地処理 ・新しいクロスの貼り付け など |
| 必須の資格 | なし |
| あると役立つ資格 | ・表装技能士 ・内装仕上げ施工技能士 ・建築施工管理技士 など |
| 年収の目安(独立前) | 約453万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・手先が器用 ・美的センスがある ・黙々と作業するのが好き |
| 向いていない人の特徴 | ・細かい作業が苦手 ・単調な作業が苦手 |
厚生労働省によると、クロス職人のうちの47.1%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
作業をスピーディーにこなし、質の高い仕上がりを提供できれば十分に高収入を狙えるでしょう。
大がかりな現場ではチームで作業することもありますが、一般住宅くらいの規模であれば基本的に個人プレーで勝負できます。
③タイル職人
タイル職人は、建物の壁面・床面にタイルを貼り付ける仕事です。
基本的には一人で完結する仕事で、美的センスがあり、空間把握能力にたけている人の独立に向いています。
タイル職人の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・下地処理 ・タイル張り ・タイルの補修 など |
| 必須の資格 | なし |
| あると役立つ資格 | ・タイル張り技能士 ・防水施工技能士 ・建築施工管理技士 など |
| 年収の目安(独立前) | 約453万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・手先が器用 ・美的センスがある ・空間把握能力がある |
| 向いていない人の特徴 | ・細かい作業が苦手 ・膝や腰に持病がある ・化学製品の臭いが苦手 |
厚生労働省によると、タイル職人のうちの44%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
タイル職人になるのに必須の資格はありませんが、タイルや接着剤の選定能力、下地処理のスキル、精密な配置スキルなどの証明となる「タイル張り技能士」の国家資格を取得すると信頼度&収入がアップしやすいです。
④左官屋
左官屋は、建物の壁や床に土・漆喰・珪藻土・モルタルなどの塗り材を塗って仕上げをする職人です。
手作業で独特の風合いや質感を生み出すことができる仕事で、建設業のなかでも芸術性の高い業種といえます。
左官屋の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・下地処理 ・塗り仕上げ ・タイル工事 ・ブロック工事 ・防水工事 など |
| 必須の資格 | なし |
| あると役立つ資格 | ・左官技能士 ・登録左官基幹技能者 ・防水施工技能士 ・ブロック建築技能士 など |
| 年収の目安(独立前) | 約453万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・手先が器用 ・集中力がある ・美的センスがある |
| 向いていない人の特徴 | ・細かい作業が苦手 ・体力に自信がない ・膝や腰に持病がある |
厚生労働省によると、左官屋のうちの38.9%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
美しい仕上げができる左官屋はとくに需要が高く、高単価な依頼が集中することも少なくありません。
美的センスが問われる左官屋は伝統的な技法も学べるので「デザインやアートに興味がある」「個人で実績をあげたい」という職人志望の人におすすめです。
⑤塗装屋
塗装屋は、家具・壁・屋根などのさまざまなものに塗料を塗る仕事です。
塗料を塗る作業は見た目を美しく仕上げるだけでなく、素材を保護する役割も担っています。
塗装屋の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・下地処理 ・塗装 ・研磨/仕上げ ・塗膜検査 など |
| 必須の資格 | なし |
| あると役立つ資格 | ・塗装技能士 ・有機溶剤作業主任者 ・足場の組立て等作業主任者 など |
| 年収の目安(独立前) | 約442万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・細かい作業が得意 ・丁寧&几帳面 ・臭い耐性がある |
| 向いていない人の特徴 | ・高い場所が苦手 ・細かい作業が苦手 ・薬剤の臭いが苦手 |
厚生労働省によると、塗装屋のうちの45.5%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
一般住宅レベルの塗装なら一人で仕事が完結しますが、大がかりな現場ではチーム作業になることもあります。
また、外壁塗装は10年〜15年ごとにメンテナンスをするのが一般的です。
そのため、ベースとして安定収入が見込め、特別塗料の施行や防水工事までできるとより高単価な依頼を受けやすいでしょう。
⑥配管工
配管工は、建物のガス管、排水管、給水管、空調設備などの配管工事をする仕事です。
用途に応じて5つの種類に分けられ、水まわりは「衛生配管工」、空調まわりは「空調配管工」、ガスまわりは「ガス配管工」が担当します。
配管工の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・配管の新設工事 ・配管の修理 ・配管の加工 ・配管図の作成 など |
| 必須の資格 | なし(※取り扱う内容によって資格が必要な場合あり) |
| あると役立つ資格 | ・配管技能士 ・管工事施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者 など |
| 年収の目安(独立前) | 約485万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・体力に自信がある ・集中力がある ・細かい作業が得意 |
| 向いていない人の特徴 | ・トラブル対応が苦手 ・狭い場所/暗い場所が苦手 ・なるべく汚れたくない |
厚生労働省によると、配管工のうちの27.7%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
ライフラインを扱う仕事のため常に一定の需要があり、食いっぱぐれる心配がすくない職人仕事の一つです。
キッチンやトイレなどの小規模なリフォームは一人で担当できることも多く、夜間対応や休日対応でより高単価な依頼を受けることもできます。
⑦電気工事士
電気工事士は、電気設備の設置・修理に必要な国家資格をもつ職人です。
電気工事士の資格には「第二種電気工事士」と「第一種電気工事士」の2種類があり、第二種は住宅や店舗、第一種はビルや工場などの大規模な工事に従事できます。
電気工事士の主な仕事内容、年収、向いている人などをみてみましょう。
| 主な仕事内容 | ・照明やエアコンなどの設置 ・コンセントやスイッチの取り付け ・分電盤(ブレーカー)の交換や設置 ・配線ルートの設計 など |
| 必須の資格 | 第二種電気工事士(または第一種電気工事士) |
| あると役立つ資格 | ・電気工事施工管理技士 ・認定電気工事従事者 ・特殊電気工事資格者 など |
| 年収の目安(独立前) | 約547万円(参考:厚生労働省) |
| 向いている人の特徴 | ・電気や機械に興味がある ・論理的に考えるのが得意 ・細かい作業が得意 |
| 向いていない人の特徴 | ・気が散りやすい ・危機管理能力が低い ・電気に対する恐怖心が強い |
厚生労働省によると、電気工事士のうちの19.5%の人が、自営・フリーランスとして独立しています(令和7年時点)。
独立すると会社員時代よりも高収入が期待でき、上位資格である第一種電気工事士を取得すると、年収800〜1,000万円を稼ぐことも夢ではありません。
ただし、電気工事士として独立するには、第二種電気工事士(または第一種電気工事士)の資格と3年以上の実務経験が必要です。
未経験からチャレンジしたい場合は、受験資格がない第二種電気工事士の取得を目指しましょう。
職人が独立を成功させるためのコツ・準備5つ
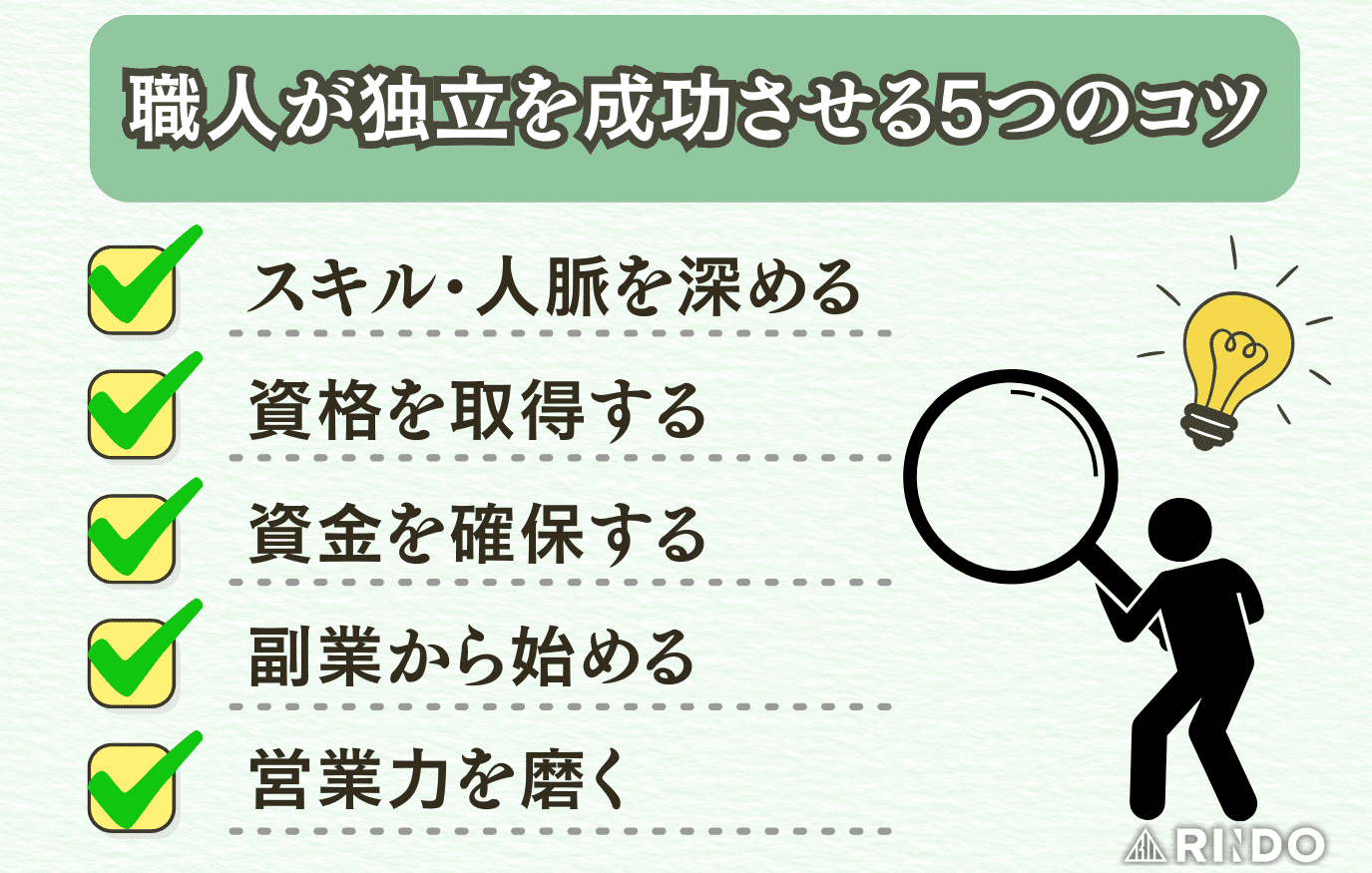
職人が独立を成功させるためには、次の5つの準備を進めておくことが大切です。
- 現職でスキル・人脈を深める
- 必要な資格を先に取得する
- 開業資金と生活費を確保する
- 副業や休日起業を試す
- 集客や営業力を磨く
ポイントは「スキルと同じくらい“営業力”も高めておく」ことです。それぞれ詳しく解説します。
①現職でスキル・人脈を深めておく
今の仕事で独立したい人は、まず今の職場でスキル&対応力を高めることから始めてみましょう。
「あの人なら安心して任せられる」と思われる職人になることが、独立成功への第一歩です。
たとえば、独立後に「知人から仕事をもらう」のと「ゼロから新規顧客を見つける」のとでは、前者のほうがハードルが下がります。
会社員時代に出会った人たちは“独立後の最初の顧客”になることも多く、満足度の高い仕事をすれば、口コミで新規顧客を紹介してもらえる可能性もあります。
また、現職でさまざまな業務を経験することで、独立後に起こりうるトラブルへの対応力が身につくことも。会社員時代にコツコツ積んだスキルと対応力は、独立後の財産になります。
②必要な資格をあらかじめ取得する
電気工事士のように資格が必須の仕事は、あらかじめ資格を取得しておくことがポイントです。
必須の資格がない仕事であっても、関連する資格を取得しておくことで次のようなメリットが期待できます。
- 仕事の幅が広がる
- ライバルと差をつけられる
- 顧客から信頼されやすくなる
資格の種類にもよりますが、基本的に資格取得には数か月〜1年ほど時間がかかります。独立を決めたら早めに勉強を始めましょう。
独立に高収入を期待する場合は、基本的な資格だけでなく、より専門性の高い資格にもチャレンジしてみるのがおすすめです。
専門性が高まり、高単価な依頼が舞い込みやすくなります。(例:第二種電気工事士を取得したら、より専門的な第一種電気工事士も目指すなど)
関連記事:補助金を使って働きながら資格取得!申請方法までわかりやすく解説
③開業資金と生活費を確保しておく
独立にはさまざまな費用がかかるため、事前に十分な開業資金と生活費を確保しておきましょう。
開業資金の内訳には次のようなものがあります。
- 道具や機械の購入費
- オフィス備品の購入費
- 材料の仕入れ費
- 事務所や倉庫の家賃
- 作業車の購入・維持費
- 保険の加入費用 など
独立をすると、仕事をもらってから入金されるまでの期間が空くことがあります。
上記のような開業資金にプラスして、当面の生活費(半年〜1年くらい)も確保しておくと安心です。
④副業や休日起業で試してみる
独立を成功させたいなら、いきなり仕事を辞めて独立するのは避けましょう。まずは、副業や休日起業で「実際にやってみる」ことをおすすめします。
副業や休日起業のメリットは次のとおりです。
- 仕事の向き・不向きがわかる
- 急な独立→失敗のリスクを減らせる
- 営業や顧客対応の練習になる など
副業や休日起業で実際にやってみることで、その仕事への向き・不向きがわかります。
「やっぱり、この仕事は自分には向いていないから辞めよう……」というリスクが減り、コツコツ貯めた資金を無駄にせずすむでしょう。
また、副業や休日起業で小規模な案件からスタートすることで、営業・顧客対応の練習にもなります。
実際に一人で仕事をこなしてみることで、独立後の課題や改善点もみえやすくなるでしょう。
関連記事:【週末林業の始め方】副業で林業をするメリット・デメリットも紹介
⑤集客や営業力を磨く
「今ある人脈だけで十分」と思える人以外は、集客や営業力を磨いておく必要があります。
今の時代に独立で成功するなら、口コミやSNSの活用が欠かせません。
たとえば、口コミやSNSは次のような活用ができます。
- Instagramで「ビフォー・アフター」の写真を投稿
- YouTubeで作業の工程や仕上がりを紹介
- ブログで施工事例やお客様の声を発信 など
口コミやSNS活用のコツは、視覚的にわかりやすいコンテンツを用意すること。
投稿を見た人がパッとイメージでき「こんな感じでやってほしい!」「この人に仕事を頼みたい」と思ってもらいやすくなります。
もちろん、今の仕事で人脈を深めることも欠かせません。デジタル集客と人脈作りの両方を進めることで、独立後も安定して仕事を獲得できるでしょう。
独立経験者のリアルな声〜職人10年目の起業〜
「独立しやすい仕事や成功のコツはわかったけど、実際のところどうなんだろう……?」と気になる人もいるでしょう。
そこでここでは、実際に職人から独立を果たした“経験者のリアルな声”を簡単にご紹介します。
今回ご紹介するのは、林業業界で職人10年目に独立を果たした、茂木さんのインタビューです。
「社長から「自分でやればもっと自由にできるからいいんじゃないか」というお話を頂いて。出資金を出すので、やってみないかと(中略)だから10年早いけど、いいチャンスかな、そこまで言ってもらえることも人生にないよなと」
インタビューでこう話されたのは、林業歴10年目の節目に自身の会社「株式会社茂木林業」を設立した茂木さんです。

画像提供:株式会社茂木林業
子どものころから漠然と「自然のなかで働きたい」と考えており、農林大学を卒業してから、森林組合・事務系職員・現場作業員・森林施業プランナーなど、林業のさまざまなスキル・経験を積みました。
「緑の雇用制度を使って入社して、最初は事務系職員としての仕事をやりましたね。そこで助成金・補助金を取りながら事業運営していくところを一通り全部経験して。林業の稼ぎ方というか、林業経営みたいなものを理解しました」
茂木さんは「緑の雇用」をはじめとした補助金・支援制度をうまく活用して、独立する前から林業の事業運営を一通り経験。そこで林業の稼ぎ方や経営ノウハウを学び、待望の独立へと一歩踏み出しました。
職人としての独立の成功のコツである「人脈」「資金」「体験」などを満遍なく実施した結果、茂木さんは想定していたより10年も早く“独立”を成功させています。
\林業への転職・独立の相談は『RINDO』へ/
\専門アドバイザーがあなたのキャリアを応援/
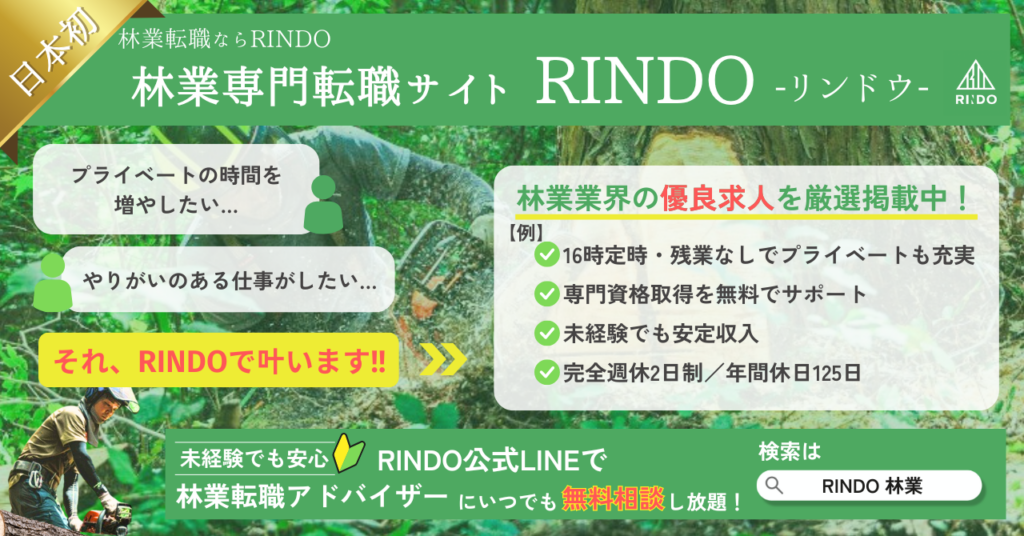
![]()
職人が独立しやすい仕事でよくある質問

最後に、職人が独立しやすい仕事でよくある質問をご紹介します。
Q1. 職人は独立したほうが儲かる?
「職人は独立したほうが必ず儲かる」とは言い切れません。しかし、独立をするとスキル・仕事量・営業力などによって、会社員時代より年収が増えることがあります。
独立後に高収入を得るためには、継続的なスキルアップ、人脈づくり、資格取得、営業活動などに力を入れることが大切です。ライバルたちより高単価な依頼を受けやすくなり、年収がアップする可能性が高まります。
Q2. 職人が独立に失敗する原因って?
職人は独立して失敗してしまうケースがありますが、よくある原因には次のようなものが考えられます。
- スキルや経験が足りない
- 開業資金や生活費が足りない
- 仕事が取れない(営業・集客が苦手)
- 事務作業が苦手で、経営管理ができない
- ケガ・病気で仕事を続けられなくなる など
なかでも多いのが「営業・集客ができない」という問題です。いくらずば抜けたスキルがあっても、集客ができなければ事業は成り立ちません。
職人が独立の失敗を防ぐためには、独立前に集客・営業スキルを身につけておくことが大切です。
Q3. 建設業で独立しやすい仕事は?
建設業のなかでも、職人として独立しやすいのは次の仕事です。
- 大工
- クロス職人
- タイル職人
- 左官屋
- 塗装屋
- 配管工
- 電気工事士
これらの仕事は「専門性が高い」「一人でも作業を完結できる」「初期費用が比較的少ない」という共通点があり、独立しやすい仕事として挙げられます。
まとめ
職人が独立しやすい仕事には「専門スキルで差別化しやすい」「一人で完結する業務が多い」「初期費用が比較的少ない」という共通点があります。
今回紹介した7つの仕事(大工・クロス職人・タイル職人・左官屋・塗装屋・配管工・電気工事士)は、これらの条件を満たす代表的な仕事です。
自分に向いていそうな仕事があれば、独立を成功させる5つの準備に取りかかり、さっそく独立に向けて動き出しましょう。
- 現職でスキル・人脈を深める
- 必要な資格を先に取得する
- 開業資金と生活費を確保する
- 副業や休日起業を試す
- 集客や営業力を磨く
あなたの“独立への第一歩”を応援しています。

